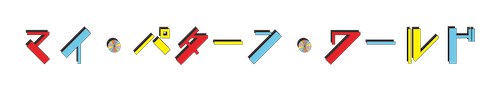私は東京を拠点に創作活動をしている、サイトウミキと申します。
主な創作内容は、模様を描くことです。
それらはデザインとしても描きますし、絵画作品としても描きます。

模様が絵画?と思われた方もいると思いますが、ジャンルで言えば「模様画・模様絵画」となります。
聞いたことがなくても全く変ではありません。
それもそのはず、日本では全く浸透していないアート分野だからです。
なぜかというのは私にもわかりませんが(笑)、模様自体は実はとても親しみやすいモノで、その面白さと魅力をもっと多くの日本人に知ってほしいと思い、このブログを始めました。
模様とは?大昔から人間の一番近くにあるアート。
まず始めに、模様といえば建築物や服などの装飾デザインのイメージが圧倒的に強いと思います。
絵や絵画と言われてもピンとこないかもしれません。
でも海外では、幾何学模様だけを描き続けている画家やアーティストは非常に多く、それらは歴としたアート作品として世に出ています。
興味のある方はInstagramで#geometricabstractionと検索して見てください。実に色々な作品が出てきますよ。
そして私も彼らのように、デザインではなく作品として模様を描くことがあります。

日本で模様といえば、何かの製品に使われる柄としてのデザインという認識が主流で、絵画作品で模様を扱う画家は少なく非常にマイノリティな作風ですが、模様自体は大昔から人間に一番近い芸術として存在しています。
それぞれの土地で生まれた民族文様
人間に一番近い芸術品?と言ってもよくわからないと思いますので、単純に民族文様を思い浮かべてみてください。
有名なモノを挙げると、ケルト紋様・アメリカ先住民のネイティブ柄・サモアやタヒチなどのポリネシアンタトゥー(トライバルタトゥー)・イスラムモスクの幾何学模様やアラベスク、、
日本で言えば、古典的な日本文様にアイヌ文様や琉球(沖縄)の文様などなど…
他にもあげたらキリがないほど、模様というのはその土地それぞれの文化として生まれ、人々の生活に根付いて存在し続けています。
世界各地の様々な地域のバックボーンから生まれた模様はそれぞれの地域の生活に密着し(家具や衣服など日常で使う物の装飾、また儀式や神聖な場で用いる装飾品として)、その洗練されたデザインは現代に至るまで伝え継がれています。

要するに、模様というのは人間が使う物の中に存在していることが大半なのです。
また幾何学模様の基となる幾何学という分野も大昔から人間の生活に密着して存在しており、知れば知るほど奥の深い世界でもあります。
デザインとしてだけでも十分に美しい模様が世界各地で見られるわけですが、それらの歴史の深さというのはイコール人間の歴史そのものでもあり、単なる装飾デザインの域を超えて芸術品(アート)としての価値があると言えるモノなのです。

単なるデザインとは見れなくなったワケ。
私は子供の頃、美術の授業でたまたま模様を真似して描いたことから急にその面白さに目覚め、世界中のいろんな模様を真似しながら、20年ほど独学で模様を描き続けました。
世界中の模様から学んだことは、”芸術品として模様を描く”ということ
どうやって独学で描き続けたのかというと、単純に世界中のいろんな模様を(民族文様からタトゥーの模様、果ては漫画のキャラクターの衣服の模様まで)色々見まくって真似しまくったのです。
そして真似をするときも、”何かに使いたい”というデザインとしてではなく「これだけの素晴らしい・かっこいいモノを自分も描きたい」という気持ちから、芸術品・アートとしてその模様たちを参考にしていた感覚があります。
単純に自分の”好き”のツボを押されまくっただけですが、イスラム芸術のアラベスクや曼荼羅模様、ポリネシアンタトゥーなどなど、精巧な民族文様を一度じっくり見てみて欲しいです。
単なるデザインの域を超えた芸術作品、そのフレーズが絶対にしっくりくるはずです。
画像は無断で貼れないので、気になる方は「世界の民族文様」とかで色々検索してみてください。
そして自分で創作して模様を描いている時は、デザインで使うことは全く考えずに、ただ楽しい!面白い!という気持ちだけで描きまくっていました。
そんな描き方を続けたせいで、気づいたら私は模様をデザインとして捉えることができなくなり、自然と”絵画”という作品として制作をする道を選んでいました。
一人の人間の哲学やアイデンティティを乗せた、模様絵画としてです。

描けるようになれば分かる面白さ
ただ、日本ではまだ模様を作品として描く作家が少ないのも影響してか、模様だけで描かれた絵画というのはさほど評価をされていないように感じます。
それは模様が装飾デザインという枠にとどまり、それ自体の面白さや魅力がそこまで浸透していないからのようにも思います。
そこで、伝え方を工夫すれば超初心者の人でも描けるのが模様ですので(実は)、
模様が描ければ自分だけの作品が作れるようになり、自分だけの作品が作れるようになれば模様の面白さも見えてくる。
そうすればもっと「模様画・模様絵画」も認知され始めるかも?
そんな魂胆を胸に、実践ワークも含めながら、「模様」について描き方以外にも色々発信していこうと考えるようになりました。
絵=リアルな具象絵画?そのハードルの高さ。
突然ですが、「美術」と言われる絵画の世界は、敷居が高いと感じる人が多いと思います。
作品に高値がついたり、超がつく有名画家の展覧会は何十・何百年経っても人気だったり、
展示される美術館自体がなんとなくそんな感じがしたり、色々理由はあるかと。
その中でも私の超個人的な見解では、その理由の一つが日本でいわゆる絵画と呼ばれる物がほぼ具象絵画だから、じゃないかなという気がしています。
三次元のモノを二次元にする絵は、実はすごいこと
「デッサンを正しく学べば誰でも絵は描けるようになる」
絵が上手い人がよく言うセリフです。
実際、物凄い下手な人でも正しい描き方さえ身につけてしまえば、目に見える物を紙に描き起こすのは不可能ではないのです。
それほど、絵の描き方には歴としたルールが存在します。

しかし。いくら誰でも描けると言っても当然、向き不向きはあります。
スポーツと同じだと考えてもらえれば、わかりやすいかもしれません。
身体の動かし方、ボールの蹴り方を先生から正しく教えてもらっても、どうにもできない子って小学校の時クラスに数人はいましたよね。
私もまぁまぁの運動音痴なので全くできなかったスポーツもあり、そう言った子の気持ちはよくわかります。
また、もし正しいやり方で誰でもそれなりにできるようになるとしたら、プロのスポーツ選手と凡人との違いはなんなのでしょうか。
当然努力の差はありますが、それ以前の向き不向き・才能やセンス、そこの違いじゃないのかなと…
やる前から諦めているようであまりいい言い方ではないのですが、事実その違いはあると思います。
同じやり方を教えてすぐ出来る人と何回やってもなかなかコツを掴めない人、どちらも存在するのが当たり前で、絵の世界も同じようなものです。

できないことに興味を持つのは難しい …
今の義務教育について詳しく知りませんが、少なくとも私の記憶では、誰もが受ける美術の授業の中で本格的なデッサンの授業はなかったように思います。
あったとしても選択科目でだけだったような…
このことから、おそらく絵は自ら選ばない限り教えてもらう事もないような分野なのです。
触れる機会が少ないとますます、三次元のモチーフを描ける人は限られてきますし、そういう絵を描く事に慣れていない人がいきなり最初から目の前の物を描くというのは、それだけでハードルが高く感じやすいです。
描き方がわかっていても、時間をかければできるようになると分かっていても、出来ない人はその前に心が折れるのが先かもしれません。汗
そのくらい、三次元の物を二次元で描くというのはそんなに簡単な技術ではないと私は感じます。
できない事に興味を持つのはけっこう大変ですよね。
敷居が高いと感じる人が多いのは、そういうことが一つの理由でもあるのかなと思います。
けれど、模様はそういった挫折の前になんとなく描けてる感覚が持てる方法というのがあります。
絵が苦手な人でも描けるのが模様!
あらかじめお伝えしておきますが、私もデッサンを基礎とした具象絵画は、正直不得意です。
これは隠していてもいつかバレるので、先にお伝えしておきます。
具象絵画に向き不向きがあると熱弁した理由はここにあります…。
模様の描き方にもルールがある。そしてそれは超カンタン
もちろん、私もデッサンの勉強はしていました。
しかし、頭で想像したものを紙に描く事と目の間にある物を描く事は、全く次元の違う描き方です。
私はデッサンをやるより前に、頭に浮かぶイメージ(模様)を描くことをずっとしてきていたので、目の前の物が想像以上に描けない自分に、非常に落ち込んだものです。
しかしデッサン同様、模様にも歴とした描き方のルールが存在します。
そしてそれは、かなり簡単で単純です。

何かをモチーフにして描写力を身につけて描く、という感覚ではなく、ある一定の法則を知れば描けるようになる、それがルールなのです。
「できない、描けない」と心が折れる前にそれっぽく出来る方法なんですよね。
それを身につけてしまえば、あとは描きたいという気持ちがあれば、結構いい感じの模様が描けるようになるんです。
模様も立派なアート。その理由は。
私も本格的に絵の道を進み始めた時、具象画が苦手なのはかなりコンプレックスでしたが、今は自信を持って絵を描いていると言える自分がいます。
それはなぜか。
おそらく、一人の絵描きとして作品を作るのに一番重要なのが画力ではなく、創作を通して発信したい自分なりの哲学やアイデンティティなんだと、創作活動をしながら理解したからです。

あくまで一般的な模様の認識は「デザイン・装飾」ではありますが、何かしらを自分の中に持ってそれを表現するという意図で描けば「模様だから違う」と言い切れる理由はなく、具象絵画や抽象絵画と同じなのだと考えています。
模様がアートかデザインか、それは作家の意図にある
逆を言えば、いくらキレイな風景画や静物画が描かれていても、そこに作家のアイデンティティや思想などが何もなければ、その作品はアートと言えるのか?ということになります。
今で言えば、AIが描いた絵画なんかまさにそうですよね。
そもそもアートは人それぞれ色々な捉え方があります。
勿論、賛否両論あると思いますが、少なくとも私が作家活動を始めてから出会ってきた作家さんには自分の思想やアイデンティティを持たない人など一人もいませんでした。
中にはガラスや炭だけを使った作品を制作する作家さんもいます。
ですので、模様ってアートなの?デザインじゃないの?と疑問に思ったら、作家がどういう意図でその模様を作った(描いた)か、そこを考えてみて欲しいと思っています。
ちなみ私も、デザインとして模様を描くこともあります。
活動を始めてからそのあたりのすみ分けができるようになり、壁紙の柄や簡単に飾れる小さい絵なんかはデザインの一種です。
特になんの哲学うんぬんもなく、見た目が良いかどうかだけで制作しています。

そんな感じの独学スタイルで、私は模様の絵画作品を制作しています。
新しい絵の描き方・ジャンルとして。
最後に。
模様やパターンの仕組みを説明した本は世の中にたくさんありますが、発想面から全てを伝えている模様の書き方の教本やサイトはあまりありません。
絵画として描く方法なら尚更です。
そういった意味で、当ブログで「模様画・模様絵画」の描き方を発信すれば新しい絵の描き方の提示になる…と言いたかったところですが、厳密に言えば新しくはないです。笑
始めにも書きましたように、日本で浸透していないだけで海外では普通に「模様画・模様絵画」を描く作家は多くいます。
そして日本は、風景画・人物画・具象画・抽象画…とわざわざジャンルに分けて鑑賞するカテゴライズ文化が強い国なので、だったら「模様画・模様絵画」というジャンルがあっても良いんじゃない?と私は考えています。
それが新しいと思われるかどうかはともかく、今の日本では「模様画・模様絵画」にスポットライトは全く当たっていませんのでニッチなモノ・マイナーなモノが好きな方はぜひその存在を知って欲しいなと思います。笑

そして自分でも模様が描けるようになれば、身近にあることも気づかなかった様々な模様にも出会う事ができ、その面白さがいい暇つぶしや趣味になってくれるかもしれません。
模様の描き方を知りたくてこの記事を見つけて下さった方はもちろん、新しい趣味がほしい方や暇すぎてつらいという方も(いらっしゃれば)、自分だけの作品を創る面白さをこのブログを通して体験してほしい、そう考えています。